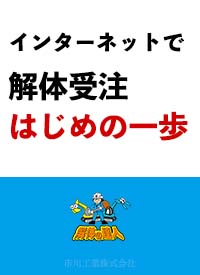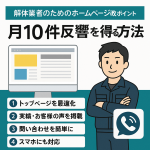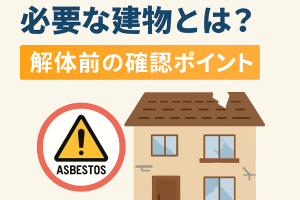🧪 はじめに|規制が「厳しく」なったのではなく「常識」になった
2025年、アスベスト(石綿)に関する法規制がさらに強化されました。
これまで曖昧だった部分が、明確な義務として制度化され、
✅ 対象工事の拡大
✅ 調査内容の厳格化
✅ 報告義務と罰則の導入
といった現場に直結する重要な変更が含まれています。
この記事では、
✅ アスベスト規制の最新改正ポイント
✅ 事前調査と報告義務の具体的内容
✅ 解体・リフォーム現場での実務的注意点
をわかりやすく解説します!
✅ そもそも「アスベスト」とは?
アスベスト(石綿)は、かつて広く使われた建材ですが、
現在では吸引による健康被害(中皮腫・肺がんなど)が問題となり、全面使用禁止に。
主な含有建材(例)
-
スレート屋根材
-
吹付け断熱材
-
ビニル床材
-
保温材(配管・ボイラー等)
築年数によるリスク目安
| 築年数 | 使用リスク |
|---|---|
| 〜1989年 | 高い(使用可能時期) |
| 1990〜2006年 | 要注意(在庫流通あり) |
| 2006年〜 | 原則なし(全面禁止後) |
🔍 強化された制度のポイント(2025年最新)
📌 改正1:事前調査が「義務化」された
-
解体・改修工事すべてに調査が必要(延床面積関係なし)
-
調査は**有資格者(石綿含有建材調査者など)**が実施
-
書面+目視だけでなく、サンプリング・分析が必要な場合も
📌 改正2:調査結果の「報告」が義務化
-
国の電子システム(石綿事前調査報告システム)にて提出
-
着工の7日前までに報告が必要
-
対象はすべての解体・改修工事(一部除外あり)
📌 改正3:虚偽・無報告には「罰則」あり
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無届出 | 最大20万円の過料 |
| 虚偽報告 | 刑事罰対象の可能性あり |
| 資格なき者の調査 | 立入検査・業務停止の対象 |
📂 報告内容と必要書類(例)
| 提出物 | 内容 |
|---|---|
| 調査報告書 | 建物概要・使用建材・含有判定 |
| 分析結果(必要時) | SEM法や偏光顕微鏡分析結果など |
| 写真 | 対象建材の位置・状態を撮影したもの |
| 調査者情報 | 氏名・資格・連絡先など |
→ すべて電子システムで提出(GビズID要)
🧭 現場での流れと対応チェックリスト
① 工事受注時に建物の築年数を確認
-
「1990年以前」→ 高リスクとして調査必須
② 有資格者による現地調査を依頼
-
自社内または外部協力会社に依頼
③ 必要に応じてサンプリング・分析実施
-
成分検査は3〜7日程度かかる
④ 報告書を作成し、7日前までに報告
-
提出後は着工許可が出てから工事開始
⑤ 除去が必要な場合の段取りも同時進行で
-
飛散防止養生・専門業者手配・自治体との相談も
💡 よくある質問(FAQ)
Q1. 木造住宅でも対象になりますか?
→ はい。構造に関わらず、解体・改修工事すべてが対象です。特にトタン屋根・天井材などに含有の可能性があります。
Q2. 解体後にアスベストが見つかったら?
→ 法令違反の可能性あり。必ず着工前の調査・報告を済ませることが重要です。
Q3. 石綿除去も自社でできますか?
→ 「特別教育」「石綿作業主任者」などの資格と、飛散防止・保護具対応などの厳格な体制が必要です。
✅ 制度対応で差がつく!解体業者が取るべき行動
-
✅ 自社内に「石綿含有建材調査者」を育成・確保
-
✅ 協力会社と連携し、迅速な分析体制を構築
-
✅ 提案時から「アスベスト対応の可否」を明記
-
✅ 顧客向けに制度解説資料・ブログを作成して信頼構築
📝 まとめ|規制強化は“信頼強化”のチャンスでもある
✅ 2025年のアスベスト規制強化により、事前調査・報告が義務に
✅ 対応の早さ・正確さが、発注元や行政からの信頼に繋がる
✅ 正しい知識と体制づくりが、選ばれる業者の条件
“石綿対応できます”が、これからの業者選定の判断基準。
法令を守る=信頼を得る時代。
準備と仕組みを整えて、解体のプロとしての価値を高めていこう!