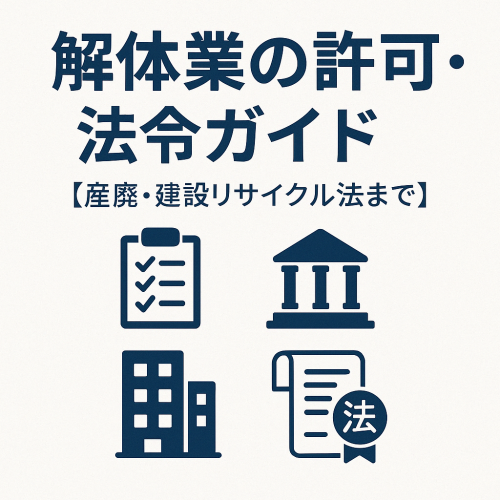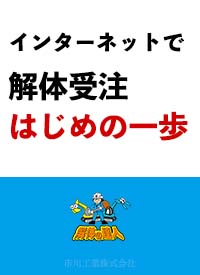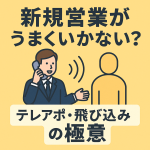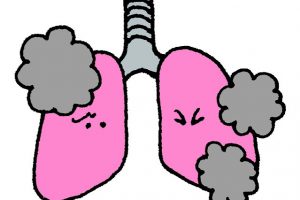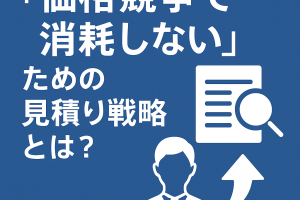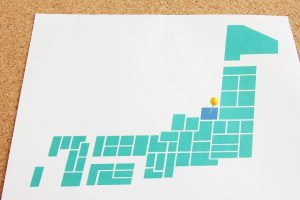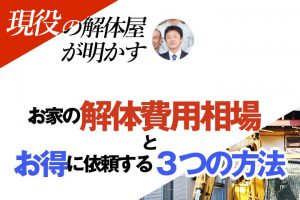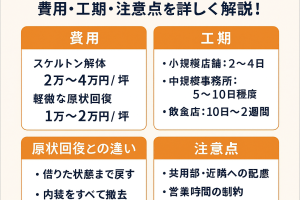はじめに|知らなかったでは済まされない“解体業の法律”
解体工事は、ただ「壊す」だけではありません。
-
建設リサイクル法
-
廃棄物処理法
-
騒音・振動規制法
-
アスベスト関連法
など、さまざまな法令・許可に基づいて行う必要があるのです。
もし無許可で業務を行えば、行政処分・罰金・業務停止などの重いリスクも。
この記事では、解体業者として必ず押さえておきたい許可・法律・手続きを、分かりやすく解説していきます!
解体業に必要な主な許可とは?
✅ ① 建設業許可(とび・土工工事業)
まず前提として、解体工事を請け負うには「建設業許可」が必要です。
-
解体工事業の区分は「とび・土工・コンクリート工事業」
-
500万円以上の工事を受けるには必須(元請・下請問わず)
-
2016年以降は「解体工事業」として独立区分も追加(要経過措置)
✅ ② 産業廃棄物収集運搬業許可
解体で発生するコンクリート・木くず・金属などは産業廃棄物。
そのため、自社で運搬・処理を行う場合はこの許可が必要。
-
許可は都道府県ごとに取得(跨ぐ場合は複数要)
-
「積替え保管あり/なし」で要件が異なる
-
許可証の提示義務あり(現場・マニフェスト等)
✅ ③ 一般廃棄物収集運搬許可(※一部ケース)
家電・家具など、産廃に該当しない“家庭ごみ系”を運搬する場合にはこの許可が必要です。
自治体ごとにルールが異なるため、市区町村ごとの確認が必須。
✅ ④ 特別管理産廃収集運搬業許可(アスベスト等)
アスベスト・鉛・フロンなど有害物を含む廃棄物の運搬には、
-
特別管理産業廃棄物収集運搬業
の許可が必要になります。
処理の際には作業基準・保護具・処分先の確認など、通常の廃棄物より厳格なルールが求められます。
必ず守るべき法律・条例まとめ
✅ 建設リサイクル法(通称:リサ法)
対象となる工事(80㎡以上の解体、500万円以上の新築等)では、
-
事前届出(自治体へ)
-
分別解体の実施
-
再資源化実績の報告
が義務付けられています。
違反すると工事停止命令・過料の対象に。
✅ 廃棄物処理法
-
産廃の運搬・処分のルール
-
マニフェストの発行・管理
-
委託契約書の締結義務
など、廃棄物処理の“基盤”を定める法律です。
※マニフェストの記載漏れ・未返送も罰則対象になるので注意!
✅ 騒音・振動規制法
住宅密集地では、解体工事に伴う
-
騒音(85dB以下)
-
振動(75dB以下)
などの基準があります。
事前の「特定建設作業届」提出が必要な場合もあるので、管轄の自治体へ確認を。
✅ 石綿障害予防規則(アスベスト)
2022年の改正により、
-
全ての解体工事で事前調査が義務化
-
作業計画届・掲示・作業基準の厳守
-
調査結果の報告(システム登録)も必須
になりました。
無届出で工事を進めると、最大50万円の罰金や指名停止の対象に。
書類・届出・マニフェストの実務ポイント
◯ 建設リサイクル法 届出書
-
解体対象の所在地の自治体へ
-
工事着手の7日前までに提出
-
書式は各自治体で異なるので注意!
◯ マニフェスト(産業廃棄物管理票)
-
電子 or 紙形式で発行
-
排出事業者が交付、収集運搬業者・処分業者へ
-
最終処分完了報告(E票)の回収確認を必ず行う
◯ 作業前チェックシート・掲示物
-
現場に「解体工事標識」「施工体制台帳」などを掲示
-
石綿ありの場合は、掲示義務+作業計画書提出
現場ごとの書類整備・管理も業者の責任です。
【注意】無許可・違反で起きるリスクと罰則
| 違反内容 | 想定されるリスク・罰則 |
|---|---|
| 建設業許可なしで請負 | 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金 |
| 産廃運搬無許可 | 5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金 |
| マニフェスト未交付 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| リサイクル法違反 | 工事中止命令+過料(20万円以下) |
| アスベスト届出違反 | 行政処分+最大50万円以下の罰金 |
まとめ|法律を“守る”から“活かす”会社へ
今や、解体業において
-
許可を持っていること
-
法律を理解していること
-
書類・管理が正確なこと
は、“選ばれる条件”でもあります。
✅ 「安心して任せられる会社」
✅ 「行政対応・安全管理ができる会社」
✅ 「トラブルを未然に防げる会社」
という評価が、受注に直結する時代です。
解体の達人では、
法令を踏まえた見積書・契約書の整備支援や、
届出サポート・書類テンプレートの提供も行っています。
法律を“守る”から“活かす”へ——
そんな会社づくりを一緒に進めていきましょう。