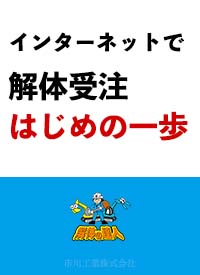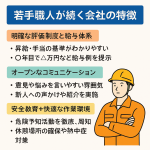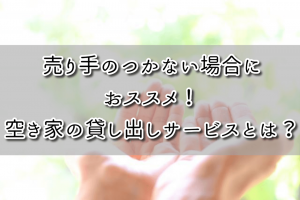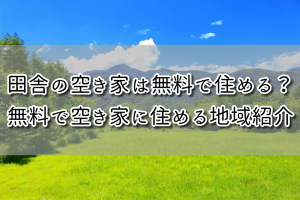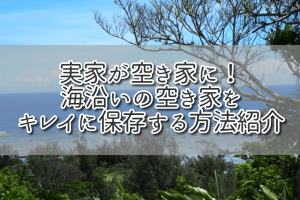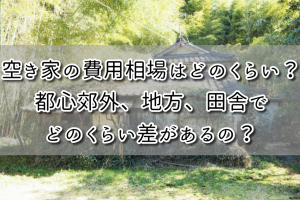はじめに|空き家対策が「待ったなし」の時代へ
今、日本の“空き家問題”は、いよいよ本格的な社会課題になりつつあります。
総務省の発表によれば、
2020年の時点で全国に約849万戸の空き家が存在。
さらに2033年には空き家率が30%を超えるという予測も出ています。
2025年以降は、
✅ 政府・自治体による空き家対策の強化
✅ 解体補助金の拡充
✅ 特定空き家指定の厳格化
などが相次ぎ、“解体工事の需要”が加速度的に増える可能性が高いと言われています。
この記事では、
「これから解体業界がどう変わるのか?」
「狙い目となる地域や業種はどこなのか?」
を具体的に解説していきます!
空き家が増える背景と今後の動き
✅ なぜ空き家が増えている?
-
少子高齢化・人口減少による“使われない家”の増加
-
相続トラブルや税金負担から、放置される物件の増加
-
不動産市場が流動化しない地方では、売却が難しくなっている
✅ 空き家特措法の強化が後押し
2023年の改正空き家特措法では、
・特定空き家の指定が拡大
・助言→指導→勧告→命令→代執行のフローが明文化
・「管理不全空き家」でも固定資産税の軽減が外れる場合あり
→ 結果として、「解体せざるを得ない」空き家が今後急増する可能性大。
✅ 国・自治体による補助金政策の継続と強化
2025年度以降も、
-
空き家除却補助
-
老朽家屋の解体助成
-
地域空き家対策支援事業
といった制度は継続される見込み。
上限引き上げや、対象要件の緩和を行う自治体も増加中です。
解体需要が高まる3つのタイプの地域
▶ ① 地方都市・中核市
-
人口は10〜30万人規模
-
市街地の空き家率が20%を超える地域も多い
-
自治体主導で“空き家バンク”と解体支援をセットで進めているケースが多い
【例】
・長野市(空き家除却上限80万円)
・福山市(特定空き家勧告強化)
・高崎市(空き家バンク連携)
▶ ② 郊外住宅地(昭和期の団地・宅地開発エリア)
-
1970〜80年代に造成された“ニュータウン”の高齢化が進行
-
相続後の「住まない・売れない」住宅が急増
→ 「高齢者が手放したい住宅」=解体依頼につながりやすい
▶ ③ 地方圏の農村エリア
-
空き家の解体に国・県の補助が入りやすい
-
建物の構造がシンプルで工期も短く済むため、利益率も高い傾向あり
→ 1件あたりの金額は小さくても、件数ベースで収益確保が可能
解体業者が狙うべき案件と連携先
✅ 狙い目となる案件タイプ
-
空き家バンク掲載物件の解体
-
相続・売却前提の実家解体
-
特定空き家に指定された物件の緊急対応
-
解体+整地+土地活用提案までワンストップで対応できる案件
✅ 連携すべきパートナー
| 連携先 | メリット |
|---|---|
| 不動産会社 | 解体後の土地売却案件を紹介されやすい |
| 行政書士・司法書士 | 相続や登記対応の相談経由で解体が発生 |
| 空き家バンク運営団体 | 解体と再活用のセットで連携できる可能性 |
| 地元自治体・地域おこし協力隊 | 地域活性化の流れの中で案件が発生 |
これからの「空き家×解体ビジネス」の動き
▶ 解体+αの提案力が求められる
単に「壊す」だけでなく、
✅ 解体後の土地活用(駐車場・貸地・ソーラー)
✅ 補助金手続きのサポート
✅ 税務・相続のワンストップ窓口化
といった**“相談窓口”としての機能**が評価されやすくなっています。
▶ 市場が伸びるのは“再建築不可”や“崖地物件”の処分系
都市部でも
・接道がない
・再建築不可
・傾斜地
といった土地では、売る前に“解体だけが必要”な案件が多くあります。
こうしたエリアでの専門対応も、今後の収益源になる分野です。
まとめ|2025年以降、「解体」は“街づくり”の入口になる
✅ 空き家問題の本格化により、解体工事のニーズは今後も増加
✅ 特に「補助金対応できる業者」「相談できる業者」が求められる
✅ 地域別に“狙い目”を絞り、地元密着で展開すれば成功確率は高い!
「空き家の悩み=解体で解決できる」
そんな時代が、すぐそこまで来ています。
あなたの地域にも、
「困ってるけど、誰に相談していいか分からない」人がきっといる。
その1人目に選ばれるための準備、始めていきましょう!