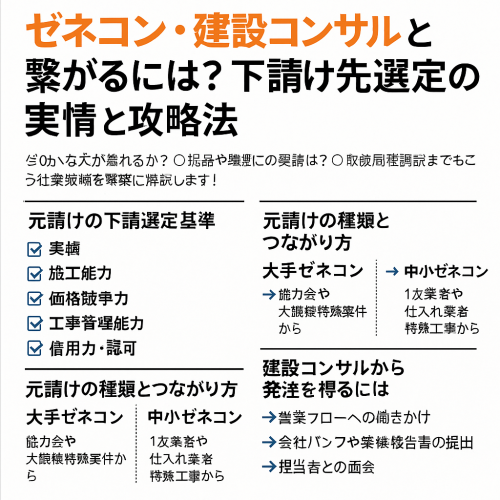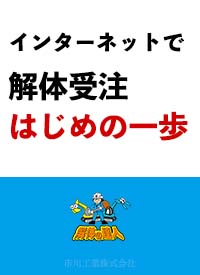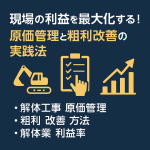「大きな案件を任されるには、どうすればいいのか?」
解体業を営んでいると、
「もっと大きな現場に関わりたい」
「ゼネコンや建設コンサルと繋がれたら仕事が安定するのに」
と考える方も多いはず。
でも現実は、
・競合が多すぎて声がかからない
・そもそも“どう選ばれてるのか”が見えない
・紹介ばかりで新規参入が難しい
そんな「閉じた業界」に見えるこの世界ですが、実は“入れるポイント”もちゃんとあるんです。
この記事では、
✅ ゼネコンや建設コンサルが下請けをどう選んでいるのか
✅ どうやって解体業者が“繋がり”を作っていくのか
✅ 選ばれるための実践的な戦略
をわかりやすくまとめていきます!
ゼネコンや建設コンサルが下請けを選ぶときに見ているポイント
ゼネコンや建設コンサルが下請け(協力会社)を選ぶ際、重視しているのは単なる“価格”だけではありません。
以下のような基準が、実際の選定に影響しています。
✅ ① 現場対応力・職人の質
-
挨拶ができる、現場がキレイ、工程管理がしっかりしている
-
「一緒に仕事をしてトラブルがない」ことが最重視される
✅ ② 資格・許可・保険体制が整っているか
-
建設業許可/産廃収集運搬/労災・賠償保険加入など
-
書類対応力=「安心して任せられる業者」
✅ ③ 過去の実績・規模感
-
「どんな現場を担当してきたか」
-
「対応可能なエリア・人数規模」など
→ 規模が小さくても、ピンポイントな対応力が光れば評価される
✅ ④ 現場担当者との“人間関係”
-
実際はココが最重要。
-
信頼できる、レスポンスが早い、現場で気が利く
→ 担当者が「また頼みたい」と思うかどうか
解体業者がゼネコン・コンサルと繋がるためのアプローチ
「じゃあどうやって、うちみたいな中小の業者が繋がればいいの?」
以下に実際に使われている“入り口”のパターンを紹介します。
▶ ① 現場での“縁”を活かす(下からの接点)
-
すでに施工中の現場に「応援業者」として入る
-
職人単位で評価されて、そこから継続依頼になるケース多数
-
特に重機オペ・手元作業員が優秀だとリピート率が高い
▶ ② 元請けの別業者から紹介をもらう
-
たとえば工務店や設計事務所などと付き合いがあるなら、
→ 「うちの解体は〇〇にお願いしてる」と紹介してもらえるようにする
▶ ③ 協力業者会・登録制ネットワークへの参加
-
ゼネコンによっては「協力会社登録制度」を持っている
-
書類提出+1回の審査(実績・保険・許可)で登録できることもある
→ 1度登録できれば、案件ごとに「見積依頼」が届く可能性あり!
▶ ④ 自社の発信で存在を知ってもらう
-
ホームページに「元請け工事対応可」「施工実績多数」と記載
-
Googleビジネスやインスタで現場の丁寧さ・安全意識をアピール
→ 「協力業者 〇〇市 解体」などで検索されることも多い
▶ ⑤ 元現場監督・OBとの人脈を活かす
-
ゼネコンや建コン出身者との繋がりがあるなら、そこが一番の近道
-
「困ってる業者がいる」と声をかけてもらえる可能性大
“選ばれる”ための実務ポイントと整備すべき体制
✅ 実務面
-
日報提出やKY(危険予知)活動ができる
-
安全書類(グリーンサイト等)を問題なく対応できる
-
工期・ルール遵守、工程通りの仕上がりを徹底
✅ 書類・管理体制面
-
建設業許可証、収集運搬許可証の有効期限チェック
-
保険証書(損害・労災)を提出できる状態に
-
会社概要やパンフレットも1枚は作成しておく
✅ 連絡スピードと現場マナー
-
担当者からの連絡に当日中に返信
-
職人への「服装・言葉遣い・喫煙ルール」など徹底
→ このあたりができている業者は、圧倒的にリピートされやすい
よくある質問と実情Q&A
Q. 協力会社登録ってどうすればできる?
A. 「〇〇建設 協力会社募集」で検索すると、WEBから申請できる企業もあります。
まずは資料請求+電話での問合せが一般的。
Q. 小規模の業者でも選ばれる?
A. もちろん可能。
「小回りがきく」「対応が早い」「人手が足りないときにすぐ出せる」など、小規模ならではの強みは大きいです。
Q. 安さで勝負すれば入りやすい?
A. 危険です。
解体工事は「安全第一」。
“安さ重視”で選ばれると、1回の事故やクレームで即切られるリスクも高いです。
まとめ|「信頼で選ばれる業者」になる準備はできていますか?
✅ ゼネコンや建設コンサルは“信頼できる下請け”を探している
✅ 技術・価格だけでなく、“人柄・対応・書類力”も評価対象
✅ 現場の中で、実績・紹介・登録制度などから繋がることは十分可能!
「うちは無理かも」ではなく、「まずできる準備から」
信頼・実績・発信が揃えば、
次に選ばれるのは、あなたの会社かもしれません。