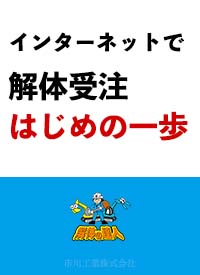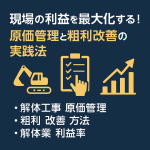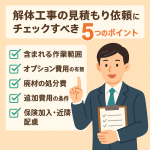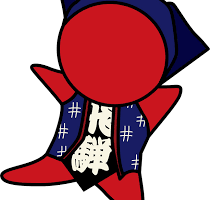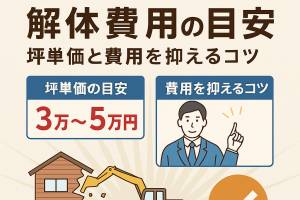はじめに|解体費用の中で見落とされがちな「処分費」

解体工事の見積もりを見たときに、
「建物を壊す費用」ばかりに目がいっていませんか?
実は、解体工事の費用の中で**大きな割合を占めるのが“産業廃棄物の処理費”**なんです。
この記事では、
✅ 産業廃棄物の種類と費用の内訳
✅ 分別とリサイクル義務
✅ 費用を抑えるコツ
を分かりやすく解説していきます!
解体工事で発生する産業廃棄物の種類とは?
解体工事で出る廃棄物は、法律上「産業廃棄物」として扱われ、以下のような種類に分類されます。
✅ 主な解体時の産業廃棄物
-
木くず(柱・梁・内装材など)
-
コンクリートがら(基礎・外構など)
-
石膏ボード(壁材)
-
金属くず(屋根材・配管・設備機器など)
-
混合廃棄物(ビニール・断熱材・プラスチックなど)
-
ガラス・陶器くず(窓・洗面台・トイレ)
-
アスファルトがら(駐車場など)
※不法投棄や不適切な処理を防ぐため、分別・処理方法が厳しく定められています。
産廃処理費用の内訳と相場の目安
✅ 一般的な処理費の内訳
-
収集運搬費(現場→処分場への運搬コスト)
-
中間処理費(分別・破砕・再資源化処理)
-
最終処分費(埋立てや再利用できないものの処分)
✅ 費用の目安(1トンあたり)
| 廃棄物の種類 | 単価目安 |
|---|---|
| 木くず | 約1.5〜2万円/t |
| コンクリートがら | 約1〜1.5万円/t |
| 石膏ボード | 約2〜3万円/t |
| 混合廃棄物 | 約3〜5万円/t |
※処分場の地域・契約内容によって変動あり
※一般的な30坪住宅の解体では、廃棄物総量=20〜40トン前後
建設リサイクル法による分別・処理の義務
平成14年に施行された「建設リサイクル法」では、
延床面積80㎡以上の建物解体工事について、分別解体と再資源化処理が義務化されています。
✅ 主な義務内容
-
木材・コンクリート・アスファルトなどの現場分別
-
処理業者への適正処分の委託(マニフェスト発行)
-
自治体への事前届出(対象規模の場合)
→ この法律に従っていない業者に依頼すると、元請け(発注者)側にも責任が及ぶリスクがあります。
処理費用を抑えるための3つの工夫
▶ ① 不用品・家具類は事前に整理・処分しておく
-
解体前に自分で整理することで、「産廃扱いされる量」が減る=処分費削減
-
リサイクル業者や地域の粗大ごみ回収なども活用を!
▶ ② 分別・再資源化率の高い業者を選ぶ
-
現場で丁寧に分別する業者は、混合廃棄物の比率が減り、処分費を下げやすい
-
「安く見えても実は雑な分別で廃棄コストが高い」業者には注意!
▶ ③ 解体時期をずらして繁忙期を避ける
-
処分場の混雑期(3月・9月)は費用が高騰しやすい
-
オフシーズン(6月・1月など)を狙うことでコスト減に繋がることも
見積書でチェックすべきポイントと注意点
✅ 廃棄物処理費の項目が**「一式」になっていないか?
→ 各種ごとに細かく記載されていると安心
✅ マニフェスト(産廃管理票)発行の記載があるか?
→ 法令順守の証明になります
✅ 処分場の名称・処理方法などが明記されているか?
→ 説明できない業者=危ない可能性あり
✅ 「解体後に発見された地中廃材」などの追加費用条件は書かれているか?
まとめ|適正処理×コスト管理で安心・納得の解体工事に
✅ 解体工事の費用には、「産業廃棄物処理費」が大きく関わる
✅ 処分費は“分別の精度”や“廃棄物の種類”で大きく変動する
✅ 「どこに、何を、いくらで捨てるか」を知ることがコストダウンのカギ!
解体工事は、“壊す作業”以上に“処分する作業”が重要です。
適正な処理がされているかを確認しながら、
安心・納得の工事を進めていきましょう!