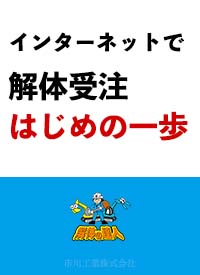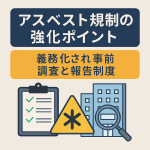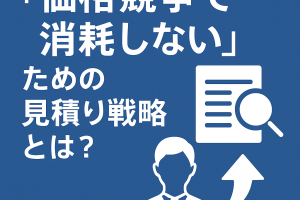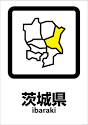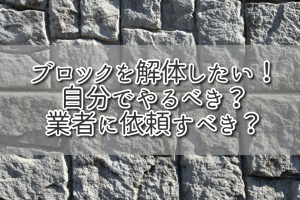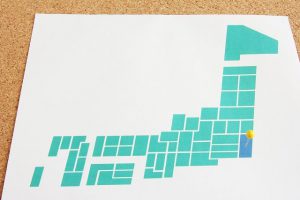👷 はじめに|「人がいない」ではもう乗り切れない
少子高齢化が進む日本の建設・解体業界。
多くの企業が「若手が採れない」「職人が定着しない」といった人材不足に直面しています。
そんな中、外国人技能実習生や特定技能外国人の活用が大きな注目を集めています。
本記事では、
✅ 2つの制度の違い
✅ 採用の流れと注意点
✅ 受け入れ企業の成功事例
をわかりやすく解説します!
✅ 外国人技能実習と特定技能の違いとは?
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能(1号) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 技術移転・国際貢献 | 人材確保(労働力補填) |
| 在留期間 | 最大5年 | 最大5年(更新可能) |
| 対象職種 | 建設分野は一部職種 | 解体業など含む12分野 |
| 日本語要件 | ほぼ不要(研修あり) | JLPT N4以上など条件あり |
| 支援体制 | 監理団体がサポート | 登録支援機関が対応 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 不可(1号)、可(2号) |
💡 ポイント
-
技能実習=「育成」型、特定技能=「戦力」型
-
解体業は両制度での受け入れが可能(条件あり)
✅ 解体業での活用メリットとは?
✅ 1. 若くて体力のある人材が確保できる
→ 解体現場に必要な「体力・持久力・機敏さ」を満たす若手が多数
✅ 2. 意欲が高く、素直で真面目な人が多い
→ 技能習得意欲が高く、先輩の指導にしっかり従ってくれる傾向あり
✅ 3. 長期的な定着が見込める
→ 特定技能では、最大5年+2号への移行でさらに長く雇用可能
→ 日本語力が上がれば、職長候補にも
✅ 4. 現場に多国籍の刺激が生まれる
→ 日本人職人にも「教える力」や「多様性理解」が育ち、現場の空気が前向きに
✅ 採用までの流れとポイント(技能実習編)
🧭 ステップ1:監理団体の選定
-
技能実習制度は、企業単独での運用不可
-
監理団体(協同組合など)を通じて受け入れる
📌 解体業対応の監理団体か、必ず確認を!
🧭 ステップ2:送り出し機関との連携
-
主にベトナム・ミャンマー・インドネシアなど
-
日本語教育・マナー研修を実施済の候補者を紹介
🧭 ステップ3:面接・選考(現地またはオンライン)
-
現地渡航 or リモートでの面接可
-
体力試験・工具扱い・意思確認など
🧭 ステップ4:在留資格取得・来日手続き
-
監理団体が書類手配
-
約3〜6ヶ月で来日・配属
✅ 特定技能の場合のポイント
-
直接雇用(派遣不可)
-
登録支援機関の活用が一般的
-
試験合格者(技能+日本語)から選抜
-
支援計画(生活支援・相談・同行など)が義務
💬 技能実習経験者が多く、即戦力になりやすい!
✅ 受け入れ事例|地方の中小解体業者が得た効果
● 新潟県の解体業者A社(技能実習生3名)
-
ベトナム人を採用
-
1年目から現場で活躍、2年目には主任補佐に
-
社内の「教える文化」が根付き、社員同士の雰囲気改善
● 埼玉県のB社(特定技能2名)
-
実習経験者を正社員雇用に切り替え
-
日本語力が高く、顧客対応・現場管理にも携わる
-
社内評価制度を整え、定着率が向上
⚠️ 注意点と導入のコツ
❗ トラブル事例と対策
| 問題 | 対応策 |
|---|---|
| 言語・文化の壁 | 先輩職人によるチューター制度、翻訳アプリ活用 |
| コミュニケーション不足 | 月1回の個別面談、SNSで日報共有 |
| 不満や誤解 | 外国人相談窓口(支援機関・社労士)との連携 |
💡 スムーズな導入のために
-
受け入れ部署の理解促進(勉強会・研修)
-
仕事以外のサポート(住居・生活用品・通訳)
-
母国文化への理解(食事・宗教・祝日など)
📝 まとめ|制度活用は“戦力確保”と“未来投資”になる
✅ 解体業界の人手不足は今後さらに深刻化
✅ 外国人材の活用は、即戦力+組織の活性化に繋がる
✅ 制度の理解とサポート体制づくりが成功のカギ!
「人がいないからできない」を「人を育ててできる」へ。
制度を正しく活かし、未来を担うチームを育てていこう!