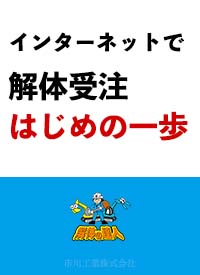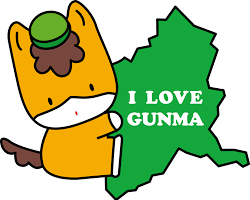火災時に必要な手続き
誰しも自宅が火災に遭うことなど望んではいませんよね。
皆さん細心の注意を払っていることと思いますが、残念ながら全ての建物は様々な事由によって火災に遭ってしまう可能性があります。
特に空気が乾燥してくる時期は注意が必要です。
今回は万が一自宅が火災に遭ってしまった場合に必要な手続きや解体方法について詳しく解説をいたします。
【火災についての関連記事はこちらから】
↑こちらの記事もお役立てください!
火災に遭ったら

火災に遭うことを想定して準備をしているという人は極めて少ないと思います。
ですが、冒頭でも申し上げた通り様々な事由によって火災に遭ってしまう可能性がありますので、建物に住んでいる以上、いつ何時火災の被害に遭うか分からないという意識を持っておくことも必要です。
いざ火災に遭ってしまったら、必要な手続きや解体などの処理をどうして良いのか分からないという人がほとんどではないでしょうか。
万が一の時に備えて今のうちに必要な手続きや解体方法などについて知っておきましょう。
まずは罹災証明書を取得する
火災に遭ってしまったら気分が落ち込むどころではなく、失望感や絶望感、あるいはこれからに対する不安などに苛まれ、冷静な精神状態ではいられなくなってしまうことがほとんどです。
しかし、そこから先の人生をしっかりとやり直すためにも前を向かなければなりません。
そこでまず必要になることが「罹災証明書」を発行してもらうことです。
罹災証明書がなければ廃材処理費用の減免や税金の免税を受けたり、あるいは融資を受けたり、または保険金を受け取ったりといったことが出来ませんので、心身ともに辛いとは思いますが出来るだけ早く取得することをおすすめします。
罹災証明書は消防機関が発行します。

「火災に遭った」という事実が確認できれば発行してもらえますので、消防機関が消火した際はもちろんのことですが、自分自身で消火をした場合でも必ず消防機関に通報をするようにしましょう。
なお罹災証明書の取得を申請する窓口は消防署や出張所にあります。
この申請には罹災者(その住宅の所有者)あるいは罹災者の血族3親等または婚姻2親等内の親族による届け出が必要ですので、身分を証明するものを忘れずに持参しましょう。
次に保険会社へ連絡をする
火災保険に加入している場合は保険会社に連絡をします。
保険金を請求する際に罹災証明書が必要になります。
なお保険会社によってルールが異なり、中には罹災証明書によって管轄の自治体の減免制度などを受けた場合、支払われる保険金に影響してくる場合がありますので、契約書を確認するか、罹災証明書を申請する前に一度保険会社に連絡をしておくことをおすすめします。
また、被害の程度を確認するためや火災の原因などを調べるために現場の調査などを行ったり、解体工事費用が火災保険から支払われることもありますので、解体は先に行わないようにしましょう。
もしその他の手続きや手配のタイミングなどに困った場合もまず保険会社に連絡してアドバイスを受けることをおすすめします。
その他に手続きが必要なもの
基本的に電力会社やガス会社は火災が発生した際に消防機関から連絡を受けています。
これは感電やガス漏れによる爆発などの二次災害を防ぐための措置です。
また同様に水の供給量を増やすために水道局にも連絡を入れているケースがほとんどです。
そのため火災があったという事実は各所に伝わっていることが多いのですが、念のため契約停止の連絡を入れるようにしましょう。
そのほか、貴重品や実印、預貯金通帳、国民健康保険証などの保険証、公的書類、国民年金手帳など公的な書類や財産に関連する書類あるいはそれに関連する物品の確認や再発行など必要に応じた手続きを行うようにしましょう。
仮住まいの手配も忘れずに
自宅が火災に遭った場合は仮住まいを探さなければならないケースもあります。
その場合、管轄の自治体に相談をすれば市営住宅などに入居できる可能性もあります。
また火災保険会社から補助金が出ることがあります。
金額に関しては保険会社により様々ですので、確認をしておきましょう。
【こちらの関連記事もご覧下さい】
関連記事の一覧はこちらから
受けられる補助制度は受ける
火災に遭ってしまったら、ただでさえ金銭的に大きな被害を被るうえ、せっかく受けられる補助制度があるのにその制度を知っているのと知らないのとではその後の生活にも大きな差が出てきてしまいます。
減免権(これが一番大事!)
自治体ごとに異なりますが、例えば所得税や住民税が減免あるいは控除されたり、火災により発生したゴミの処分費用なども東京都23区では引き取り料の9割減額されるなど多くの自治体で減免・控除を受けることができますので、確認をしておきましょう。
解体業者に連絡をする
消防署や警察署あるいは火災保険会社による火災現場の現場検証が済むと、火災現場に入れるようになります。
そのタイミングで解体業者に連絡をするのですが、通常の解体をするよりも精神的・時間的に余裕がない場合がほとんどです。
そのため、見積もりを1社や2社しか取らずに決めてしまったり火災現場の解体に慣れていない業者にお願いしてしまったりして、必要以上の費用がかかってしまうという可能性も少なくありません。
少しでも金銭的な負担を少なくするためにも、次に紹介するポイントを押さえておきましょう。
火災物件を解体をする際に注意したいポイント
1:時間的制約がある中でも2社以上は見積もりを取りたい
火災直後の冷静でない精神状態の中につけ込んでくる解体業者がいることも否定出来ません。
特に解体業者の方から声をかけてくる場合は注意が必要です。
場合によっては数百万円も金額が変わってしまうことがありますので、必ず2社以上から見積もりを取ることを心がけましょう。
2:燃えていないゴミや火災ゴミに関しては事前に処分をしておく
火災現場の解体は廃棄物やゴミなどを分別しながらの作業になるため通常の解体作業よりも手間がかかります。
燃えていないゴミや火災によって燃えた火災ゴミなどの処分を解体業者に依頼すると高くついてしまうことがありますので、事前に自治体の補助制度を受けるなどして処分しておくことをおすすめします。
3:火災現場の解体に慣れていない業者は避けたい
火災現場の解体は、廃棄物やゴミを分別しながらの作業であったり、半焼などで倒壊の恐れがあるなど通常の解体作業よりも手間やリスクが大きいケースがほとんどです。
火災現場の解体に慣れていない業者の場合、日数や作業に手間取ってその分の費用も請求される可能性がありますので注意しましょう。
なお、火災現場の解体に慣れている業者だとしても一般の解体よりは作業や処理に手間がかかることが多いため、費用はある程度高額になってしまうことは避けられないかも知れません。
火災保険会社が解体費用を補助してくれるケースでは、事前にしっかりと保険会社と相談をしてから決めるようにしましょう。
家が火事になったら…
火災は一瞬にして財産や大切な命をも奪ってしまう非常に恐ろしいものです。
願わくば誰もが火災に遭って欲しくありません。しかしながら現実として火災に遭ってしまうこともあります。
火災に遭った直後はその現実を受け入れることが出来なかったり、前向きに気持ちを切り替えることが非常に難しいことと思います。
ですがその先の人生をしっかりとやり直していくためには、手続きや手配を先延ばしにしていても始まりません。
しっかりと先を見据えて必要な手続きや手配を行うようにしましょう。
また火災保険などの契約内容、自治体の補助制度などについてもしっかりと確認をしておくようにしましょう。
知識としては必要ですが、実際にこの情報が役に立つことがないことを願っております。
【こちらの関連記事もご覧ください】